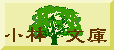

管理人です。
最近、掲示板荒らしと判断せざるを得ない書き込みが有りました。
この掲示板は、ミステリーについて、楽しく気軽に話し合える場として、設置しています。
冒頭に記述してある趣旨に反する書き込みに反する書き込みは、削除します。
不規則発言は、止めてくださいね。
それから、この掲示板CGIには、元々荒らし対策が組み込まれていましたが、その一部を表に出しました。
管理人権限で削除いたしました
しつこいぞ莫迦。No.1181とNo.1182を投稿した莫迦、おまえのことだ。しつこい男はほんとにお姉さんから嫌われるのだぞ。まだわからんのか。それにしてもおまえはどうしてそんなに情けないのだ。マニュアルどおりにしか接客のできぬコンビニやファーストフードの店にばかり行きつけてると、お前のような莫迦はいよいよ莫迦になってしまうものらしい。つけあがるな。文句があるのなら関係者に直接いえ。それもできぬ根性なしが偉そうな口を叩くな。掲示板に匿名で悪口雑言を書き連ねるな。卑劣な真似をするな。おまえのそのしつこさの理由を考えてみろ。おまえにとっての「厭うべき何か」を考えてみろ。おまえはおまえのねじくれた傲慢さに思い当たるはずだ。二度と来るな。
■小林文庫オーナー様
まーたカチンと来ましたのでできるだけ差し障りのない文面にして投稿いたします。差し障りがあるとお考えでしたら削除をお願いいたします。余計なお手数をおかけして申し訳ありません。
そういったような次第で、探偵嫌いにとっての「厭うべき何か」を深いところまで探ってゆくと、最終的には二十世紀や現代文明といったものにぶちあたってしまうのではないかという気がいたします。三島由紀夫や司馬遼太郎の場合はより直截に、探偵嫌いは戦後社会への違和感の現れ、戦後社会を成立させてしまった基盤への拒絶反応であったといえるかもしれません。
むろん単なる思いつきにすぎず、公表するのも憚られるしろものですが、探偵嫌いに関して私見を申し述べました。
ここで瀬戸川猛資の『夢想の研究』に戻りますと、私が面白いと思ったのは次のくだりです。
《ミステリ・ファンの多くは自覚していないけれども、世にミステリ嫌いが存在する理由はこの点にあるのではないだろうか。
探偵たちよ、お前たちは何故そんなに他人の謎や秘密を嗅ぎまわるのだ? そんなことばかりしているお前たちの心の中にこそ謎がひそんでいるのではないか?》
「世にミステリ嫌いが存在する理由」について、あるいは「探偵嫌い」について、ミステリファンのみなさんはいったいどんなふうにお考えなのかなと、たいへん興味深く思う次第です。
■岩堀様
そういったような次第なのですが、「変質的な詮索癖」に関して申しますと、これは白い豆腐も赤い照明を当てれば赤く見えるといったことだと思います(なんという比喩なのでしょう)。
「ある対象を徹底的に調べる」という行為も、見る人によって見方は当然異なります。「根元的には皆同じ」ものが、司馬遼太郎の例で申しますと、探偵の場合には了解不能な「変質的な詮索癖」に見え、文倉平次郎の場合には「人間の情熱というもののふしぎさ」に映ったということではないでしょうか。
たとえば書誌作成にも「情熱」は必要でしょうが、人によっては、あるいは門外漢にはそれが「妄執」と感じられることもあると思われます。私自身の体験をいえば、『乱歩文献データブック』を編纂していたとき、それを聞きつけてある日刊紙の東京本社文化部から名張市立図書館に女性記者の方が取材に来てくださったのですが(このときの記事は結局ボツになったようです)、できていた原稿をしばらく眺めていらっしゃったそのお姉さん、ふと顔をあげ、感に堪えぬといった感じで、
「よくもこんなにし」
と呟いたなり口をつぐんでおしまいになりました。おやお姉さん、「し」のあとに「つこい」とか「ゅうねんぶかい」とかいいかけて危うく踏みとどまったな、と私は思ったものでしたが、こうした場合、しつこいだの執念深いだのはむしろ褒め言葉です。素人が見てもそれがわかるくらいのものでなければ、とても一人前の書誌とは呼べないのではありますまいか。ぱらぱら眺めていたお姉さんがいきなりそれをほっぽり出し、
「ああ、これをつくった男にだけは絶対抱かれたくない」
と全身に粟を生じさせてしまう。よくできた書誌とはそういったものではないかと思われます。情熱と妄執はいくらでも言い換えが可能であり、了解不能な妄執はやはり気色の悪いものだと判断される次第です。
何の話をしておりましたのやら。とりとめがなくて申し訳ありません。
●馳星周さんのミステリトーク
身も蓋もない宣伝をさせていただきます。
わが名張市は年に一度、日本推理作家協会とミステリチャンネルの協賛を頂戴してミステリ講演会を開催しております。今年は10月13日土曜日に催され、馳星周さんが「現代ミステリと世相の関連」と題してお話になります。お近くの方はどうぞお出かけください。
きのう名張市役所のミステリ講演会担当職員と話をしましたところ、この職員は江戸川乱歩賞授賞式で馳さんとお会いし、当日の講演内容が「ロマン・ノワール(暗黒小説)について」「新宿歌舞伎町最新(裏)事情について」「サッカー(ワールド・カップ)について」といったものになるとお聞きしてきたそうです。講演会の前評判は上々とのことですが、
「ここでもうワンプッシュしたい」
と申しますので、前途ある青年職員の意を体して、僭越ながらこちらの掲示板でワンプッシュさせていただく次第です。詳細は上記 URL の名張市オフィシャルサイトでご覧ください。
少し前に書誌目録のことと、京都の H書房のことが話題に上っていました。
そのとき書こうと思ったのですが「ただの自慢話じゃないか」といったん
お蔵にしたネタがありまして、思い直して書いてみることにします。
H書房の目録で個人的に嬉しかったのは「探偵実話」昭和25年12月号、第
1巻第 6号(世界社)。
数年前のミステリ・マガジン読者欄で研究家若狭邦男氏が買入れ広告を出
していたのを覚えていたので「まぁ注文多数だろうな」と思いつつ保険で
注文したら、あっさり当たってしまった。うーん、だれも見てなかったの
だろうか?
さっそく若狭氏へ連絡したらちょうど未架蔵の号だったそうで「それなら
どうぞ」とお譲りしたらたいへん喜んで戴けて、あれはいいことしたなと
思っています。
若狭氏は「戦後探偵小説雑誌掲載目録」の作成を企図されていて、現在ま
でに「探偵倶楽部」106冊を完全収集 (「怪奇探偵クラブ」「探偵クラブ」
含む)、あとは「探偵実話」第 1巻第 2号および 4号の 2冊と、昭和26年
が数号残すところまでこぎつけられたそうです。
1冊 2万円出すと「ミステリマガジン」1998年12月号の読者欄では告知さ
れておられました。もし協力できるという方がおられましたらぜひよろし
くお願い申し上げます。連絡先等詳細は同号をご参照下さい。
P.S.
『豚と薔薇』ご希望の方、目録で見つけました。まだあるかどうかは分かり
ませんが。
http://bookbigbox.com/zanmai/new/new0805.htm
司馬遼太郎が死ぬまで 15年戦争時の参謀本部を唾棄しぬき、批判しぬいた事
は有名です。ノモンハン戦についての小説は生存者への取材など進めたもの
の、ついに書かれることなく終わったのですが司馬はこの事について語って
います。「ノモンハンを考えると頭の血管が切れてしまいそうになる」
司馬は 2年間満州 (現中国東北部)の戦車隊に駐屯、曰く「軍人将棋のような」
旧軍の思考を身を持って体験させられたのが作家の原点となりました。
ロシアの戦車部隊にどうやって対抗するのですか? と尋ねれば「日本にも戦車
はある」。ここでは性能差も補給の問題も他との連携もそもそも台数すらも考
慮外で、戦車があるというだけで対等なのである。それじゃあ軍人将棋じゃな
いか。
上のような例をいくつも実見してきた。そして青年司馬は考える。ここにはど
こにもプロの「合理性」がない。観念だけで戦に勝てるのならばプロの軍人な
どいらない。
なぜこんなになってしまったのだろう。昔からこうだったのか。否、明治時代
は、日露戦争までは違っていた(坂の上の雲)
司馬にとって明治を明るく書くことが、すなわち空論と観念で何もかもだいな
しにした昭和戦争時代への批判だったのでしょうか。
フランス文学者で評論家の鹿島茂氏がこのようなことを言っています。
「司馬史観というのはじつに単純なものである。一言で言って "腹が減って
は戦はできぬ" である」
身も蓋もないくらいあまりに単純な一言ではあります。ですが、司馬が好んで
描いた竜馬や高田屋嘉平(菜の花の沖), 秋山兄弟や児玉ら日露の参謀といった
"合理主義者" に共通するのは、けっきょくこの一言でしょう。
合理主義とはけっきょくこれではないか、と。地を這うような現実主義をしっ
かり見据えてイデオロギー(司馬はこの語を "正義体系" と訳していた) を避
けぬいた。
なんだか舌足らずもいいところですが、「大義名分論或いは正義体系への徹底
的な不信」と「腹が減っては戦はできぬ(虚飾のない現実主義)」の二本をキー
ワードにすれば、対蹠的に語られることの多い司馬遼太郎と山田風太郎はあん
がい異貌の双生児なのではありますまいか。
*
ところで思い出しました。『豚と薔薇』の併録作品は「兜卒天の巡礼」、日ユ
同祖論にハマった老人の行く末を描いた作品でした。新聞記者時代たまたま出
会った日ユ論者(というのか… )がひじょうにけったいで印象に残っていたのを
モチーフにしたそうです。
「作家になってからは、論の内容よりもむしろその精神構造のありようが興味
深かった」とあとがきにはありました。
なんだか「豚と薔薇」と通底してくるものが感じられます。
それにしてもなぜ「薔薇」なんでしょうか?
>芦辺様
確か、本日打ち合わせですよね。
どのように決定しましたでしょうか。ぜひ、発売の予定と、タイトル、神津の分だけでもお教え下さい。よろしくお願いいたします。
りえぞんさま、
もう何度御礼をいってもいい足りません。どうもありがとうございます。これでブシュウは大丈夫だと思います。しかしまだまだわけのわからん人名は多いもので、特に「化人幻戯」の大河原侯爵の蔵書には悩まされています。ウイスロウの「ローマのカタコム」なんで全くのお手上げです。りえぞんさんは御存じですか?
アルゼリアは文脈からすると学者の名前だとは思うんですが、移植の歴史をみてもせいぜいウルマンとかカレルぐらいしかのっていなくて…。
芦辺さま、
はい、Sさんはネットはやっていません。本人いわく「インターネットまで始めたら取り返しのつかないことになる」。それはたしかにある…。
桜さま、
ナダ出版センターの「日本におけるシャーロック・ホームズ」ですね。あれは買わなくては…とおもっているのですが、まだ買いそびれています。友人からみせてもらったのですが、かなりの内容のようです。
■芦辺拓様
ご意見ありがとうございます。「大衆主導の社会への憎悪」「エリート支配への幻想」の件、いかにも芦辺さんらしい(あるいは、いかにも森江春策探偵らしい、というべきでしょうか)批判精神にあふれた仰せだと思いますが、当方には司馬作品に関する知識が皆無だということもあって、にわかには判断できかねる次第です。しばらく考えてみたいと思います。
●探偵嫌い
まだつづいております。
補足その二として、新潮文庫『彼岸過迄』に収録された柄谷行人さんの「解説」から引用しておきます。この「解説」には乱歩の「D坂の殺人事件」への言及も見られるのですが、柄谷さんは乱歩作品の熱心な読者ではないらしく、デビュー当初の明智小五郎をいささか誤解していらっしゃるように見受けられます。といったようなことはまあいいとして、いきなり「第二に」と始まって前段とのつながりがつかめない引用ではありますが、「探偵」の二十世紀性とでもいったものについて述べられた主旨はこの部分だけでおわかりいただけるはずです。
《第二に、十九世紀末の小説における「探偵」の出現が重要なのは、それがマルクスの経済学批判やフロイトの精神分析と平行していることである。たとえばホームズの推理は、決まってヴィクトリア朝のイギリスにおいて上品にすましかえった紳士たちの過去の犯罪(おもに海外植民地での)をあばきだすことに終る。それはつねに歴史的な遡行なのである。同様に、マルクスは自明視されたイギリスの資本制社会とその経済学を批判し、その歴史的「原罪」(資本の原始的蓄積)に遡り、さらに貨幣形態そのものの起源にまで遡行しようとしたし、フロイトは市民社会における意識の自明性を批判し、それをいわば隠蔽された「犯罪」(父殺し)にまで遡行しようとしたのである。つまり、彼らも実証的な知に反する知としての「探偵」なのだといってよい。》
しかし、やっぱり前段は必要か。文中に《実証的な知に反する知としての「探偵」》とありますのは、警察的実証主義に立った探偵に対立する、「実証主義知性にとって見えないような謎を解明する知性主義」のことです。この「解説」では『彼岸過迄』に描かれた「探偵」が、「其目的が既に罪悪の暴露にあるのだから、予じめ人を陥れようとする成心の上に打ち立てられた職業である」ところの探偵と、「自分はただ人間の研究者否人間の異常なる機関が暗い闇夜に運転する有様を、驚嘆の念を以て眺めていたい」という探偵とに分類されています。
《後者の「探偵」は、犯人を捕えることに関心をもっていない。彼の関心は、犯罪の形式的な側面にしかない。むしろ彼は犯罪者以上に善悪に無関心なのである。この種の「探偵」はポー以後の推理小説の産物であって実在しない。実在するのは、私立探偵といっても、「警視庁の探偵」と大差はない。その目的は「罪悪の暴露」にあり且つ実証的である。小説でいえば、自然主義である。漱石が探偵を嫌うというのは、文学でいえば自然主義を嫌うというのと等価である。ポーが作りだした探偵(デュパン)は、そのような警察の実証主義に対立する。しかし、それはたんにロマンティックなのではない。他方で、それは実証主義知性にとって見えないような謎を解明する知性主義でもある。》
で、マルクスもフロイトもそうしたタイプの探偵だったという寸法です。漱石の探偵嫌いは自然主義嫌いと等価だという指摘は、私にはちょっとどうかなと思われるのですが、というか、この「解説」に見られる「探偵」の分類そのものにいささか無理があるようにも思われるのですが、
あばきたてる、
暴露する、
奥底にあるものをつかみ出す、
といった「探偵」の二十世紀性を指摘する文章のひとつとして、ご紹介申しあげる次第です。
平山さん、いろいろな情報に刷り込まれていたのでしょうか、私の書き込みはペンディングとさせてください。
ご存知の、ドイル邦訳史をかかれた新井さんの基本文献は是非入手したいです。
昨年出された、松原一枝著『改造社と山本実彦』南方新社(鹿児島)には、ドイル全集の記述がありませんでした。
ドイル全集、第1巻がダブりになりました。あぁ、また、本がふえました。
巽さん、大阪圭吉さんの、文庫解説。読むのが楽しみです。
芦辺さん、今日ですか、少年探偵の復刊が待ち遠しいです、高木さん以外はどのようなラインアップとなるのでしょうか。
>平山さん
南湖さんの講談「ルパン対ホームズ」、ホームズファンの方々のMLで流してくださったとは幸甚です。となると、前述のように《ルパン同好会》のみなさんにもお知らせしなくちゃいけませんが、あそこのHさんもSさんも確かネットやってないんですよね。
さて、明日は光文社で神津ジュブナイル&ビリーパック会議であります。こんな仕事ばかりだと楽しくていいですが、そうは参りませんね。ひー。
派手に化けたのでもう一回トライしてみます。
彼の早すぎた埋葬に関する文献の名前ですが、手元の本 Carrington and Meader "Death", 1913 によると
Traité des Signes de la Mort et des Moyens de ne pas être Enterré Vivant. Paris, 1849 (死の兆候および生き埋めの防止法に関する論考)
ということです。ただしこの↓サイトを見るとブシュウは
http://digilander.iol.it/lmeneghelli/Libri_Storici/Libri_Sto_Desc/Descr_B/libri_st_descrizione_b_4.htm#B00260
1883年にも"Les signes de la mort"(死の兆候)と題する本を出版しているようです。
>アルゼリア
これは難しいですね。第一アルゼリアが人名なのか地名なのか、それさえ分かりません。乱歩が「有名な」と書いているところを見ると当時は有名だったのでしょうが・・・。なにか分かったらまたお知らせします。
芦辺さま、
御役に立てたようで、うれしいです。ホームズクラブのメーリングリストに情報を流しました。沢山の人がききにきてくれるといいですね。南湖さんのHPもみましたが、なんと芦辺さんも壇上で御話になるとは!関西方面のかたはみのがせませんね。
巽さま、
ありがとうございます。まずこのブシュウでまちがいないとおもいます。あとは彼がかいた早すぎた埋葬に関する文献の名前ですが、さすがにこれは難しいかもしれませんね。
アルゼリアはどうやらワンタン屋に続いて迷宮入りのようです…。
桜様、中さま、りえぞん様、オーナー様
いろいろお声をかけていただきありがとうございました。また、楽しく拝見させていただいております。
平山様
ブーシェの履歴は『早まった埋葬』には載っておりません。ただ、パリ大学医学部教授だったとありましたので、その限りでは矛盾していないでしょう。なお、もしかすると、この本、『黒死館殺人事件』の参考書であった可能性も考えられますので、ひまになったら対応関係をチェックしてみたいと思います。
>中さん
お説、ここに至ってアッと声をあげそうになりました。司馬遼太郎の推理小説嫌いと三島由紀夫の『Yの悲劇』批判――確かにつながってくるようです。ところで、ここに両作家の「大衆主導の社会への憎悪」「エリート支配への幻想」を見てしまうのは例によって僕の僻目でしょうか。
桜さん、
横溝正史が別名義でドイル全集で翻訳しているとは知りませんでした。ちくま文庫の書誌にもそれは言及していなかったと思います。ちなみにどれが別名義なのでしょうか?
きのうの書き込みをいま読み返したのですが、文中に「黄色い下宿生」とありますところ、これはむろん「黄色い下宿人」とするべきでした。どうしてこんなミスを犯してしまったのか。それまでに山田風太郎の名前もさりげなく記して着々と布石を打ってきたというのに、肝腎の勘どころで見事に滑ってしまいました。まだまだ修行が足りません。
さて、三島由紀夫の「奥底にあるものをつかみ出す」は、推理小説に関して述べられた言葉ではありません。昭和44年から45年にかけて発表された「日本文学小史」の冒頭に見える、二十世紀的思考方法なんてものについて書かれた言葉です。
《奥底にあるものをつかみ出す。
さういふ思考方法に、われわれ二十世紀の人間は馴れすぎてゐる。その奥底にあるものとは、唯物弁証法の教へるものでもよい、精神分析学や民俗学の示唆するものでもよい、何か形のあるものの、形の表面を剥ぎ取つてみなければ納まらぬ。》
三島由紀夫は推理小説嫌いを公言していましたし、昭和35年に書かれた「推理小説批判」は、なにしろ「Yの悲劇」を批判した内容とあって『名探偵読本 エラリイ・クイーンとそのライヴァルたち』(パシフィカ)収録の座談会でも言及されていましたから、ミステリーファンの方にもよく知られているかと思います。そして三島が、推理小説以上にフロイトを嫌っていたこともまた周知の事実です。
などと書き始めると、はっはーん、三島のフロイト嫌い民俗学嫌いを漱石の探偵嫌いにリンクさせて、文明批判がどうの二十世紀批判がこうのなんてところに話をもちこむつもりだな、とお察しの読者もおありかもしれません。お察しのとおりです。
ある種の作家にとって(むろんそこいらの三文作家のことではありません。三文作家のみなさん、どうもすみません)「探偵」という存在あるいは行為は、三島の言葉でいえば二十世紀の人間の思考方法を一身に、しかもきわめて卑小な形で体現した唾棄すべきものと映ったのかもしれないということです。司馬遼太郎の探偵嫌いにしても、根っこのところにはそうした問題が存在していたのではないかと思われます。つまり彼らの探偵嫌いは、自身がそのなかで生きていた二十世紀とか、あるいは現代文明とか、それとも近代とかいうものに対する一種の拒絶反応だったのではないかと愚考される次第です。
というところで終わりにしてしまおうかとも考えましたが、補足する意味で「日本文学小史」から、三島が民俗学や精神分析について述べたくだりを引用しておきます。
《民俗学者の地味な探訪の手続は、精神分析医の地味な執念ぶかい分析治療の手続に似てゐる。個々の卑小な民俗現象の芥箱の底へ手をつつこんで、つひには民族のひろく深い原体験を探り出さうといふ試みは、人間個々人の心の雑多なごみ捨て場の底へ手をつつこんで、普遍的な人間性の象徴符号を見つけ出さうといふ試みと、お互ひによく似てゐる。かういふことが現代人の気に入るのである。マルクスとフロイトは、西欧の合理主義の二人の鬼子であつて、一人は未来へ、一人は過去への、呪術と悪魔祓ひを教へた点で、しかもそれを世にも合理的に見える方法で教へた点で、双璧をなすものだが、民俗学を第三の方法としてこれに加へると、われわれは文化意志を否定した文化論の三つの流派を持つことになるのである。》
それほど補足になっていないかもしれませんが、本日はこのへんでお開きといたします。
平山さん、コナン・ドイル全集が最近の目録では、かなり高めででていました。横溝さんの別名義の翻訳もありますね。
そこでは、博文館の世界探偵小説全集も、函付で、均一棚で、ほとんど揃いで見つけたこともありました。
たしかに、復刊も必要かもしれません。
「彷書月刊」10月号。特集 夢の久作、喜国さんのエッセイもあります。もう一度最初から読みたいと思った、とありますが、私もそう思いました、読みおわった瞬間に。
末永さんの、久生十蘭の捕物帳についての原稿では、初出誌について、未確認のものがあることが記されています。佳境にはいりこんできました。
司馬遼太郎の推理小説「豚と薔薇」を巡る一連のレス、たいへん興味深く
拝読させていただいております。
好きなものよりも嫌いなものについて書いた文章の方が、あたわず心情の
深いところを吐露したかたちになっている。面白いものではないでしょう
か。
「鏡地獄」のタイトルとここぞとばかりすかさず(おそらくは嬉々として)
使われたあたりもよかったです :-)
No.1139の芦辺さんのご意見も一瞬唸らされました。現在光文社文庫から
刊行中の山田風太郎ミステリー傑作選の第 5巻解説で縄田一男氏が「司馬
遼太郎と山田風太郎の読者数が完全に逆転する日がくれば」云々と書いて
いましたが、このくだりの意味が少し分かりやすくなったような。
# まず来ないだろう、となぜか少し暗くなったりしたりして
でも、たしかに司馬が自由民権運動について書いたものは寡聞にして知り
ません。あるんでしょうか?
かろうじて(かなり強引な引っ張り方ですが)「明治維新にはろくな革命思
想がなかった、せめてこの動乱期にルソーの一冊でも訳されていれば、そ
ののちの日本の経緯はどれだけ変わっていたものだろうか。中江兆民によっ
て「自由論」の題で邦語になったのは明治十年のことである」
くらいしか思い出せません。ほんの為書きですねこれは。
もし「豚…」が再録されるとすれば、あんがいミステリのアンソロジー
ではなくて司馬の研究本(もちろんあとがきも含めて) でかもしれません。
特別殺人課・多々野啓二シリ−ズ・全5回作品の中から、今回は、第2回作品「黒と黒」を本人の実際の声で、ドラマチックに事件の経過を進めていくインタ−ネツトドラマがオ−プンしました。前編を聞き、推理問題の回答を応募したかたに解決編を紹介する仕組み。また、「黒と黒」の手作り本を購入されたかたの中から賞品もあげちゃう。この事件を解決するのは、あなたです。一度のぞいてみてやってくだしゃんせ。
>文雅@神月堂
ご意見、大変よくわかります。光文社の担当氏にも見てもらいました。ただ、収録作品を見て残りの作品を古本屋へ探しにゆくステップのことまでを想定すべきか、それともよりよい作品で初対面の読者の度肝を抜くことを優先すべきか……今週末、東京で論議してきます。
>平山さん
ホームズファンのみなさんにご吹聴いただけるとはありがたいことです。ぜひ、ご参集ください。あ、ルパンのファン諸氏にも伝えるとしましょう。ちなみに、これは講談「怪盗ルパン」が『評判講談全集』に収録されているという情報をいただいて、南湖さんが資料を当たった結果ですから、やはりそちらのおかげといえましょう。
芦辺さま、
「ルパン対ホームズ」が実演になるとは実に愉快です。はたして私がお役に立てたかどうかはわかりませんが(おそらく南湖さんは『評判講談全集』を御存じでしょうから)、とにかくホームズがでるというのは愉快です。さっそくホームズクラブの連中にも知らせてやりましょう。
桜さま、
改造社のドイル全集が二千円ですか! 私は全部はもっていません。なんとうらやましいことでしょう。あれはあのままにしておくのがもったいですね。どこかで復刊してくれないでしょうか。横溝正史訳もありますし。(自分でやったのかな?)田中早苗は版権切れていますけど、ほかの和気律次郎とか石田幸太郎などはいつなくなったんでしょうか。いっそ自分でふっこくしてみようかな。
芦辺さん、唐沢俊一さん編集になります『少年探偵の逆襲』のこと、その後、HPにでてこないですね。
文雅@神月堂さん、ご教示ありがとうございます。雑誌「探偵王」、おげまるさん作成の資料で確認しました。最終回まで確認されておられるようでした。
二日前、「コナン・ドイル全集」改造社、昭和6.12から昭和8.11、全8冊、函付を見つける。全部で2千円。
重いので、後日取りに行くことにしました。紐にくくられていたので、中味を確認していません。主人にはなしをききますと、まだ、ほかにも、全集ものがあるようでした。
| Powered by T-Note Ver.3.20 |