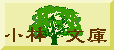

>こんな出版社ちょっとないっす。
のあとに意味不明な1行が入りました。春陽堂の呪いか?
中さん
『春陽堂書店発行図書総目録』の一番ダメなところは著者索引、タイトル索引がついていないことですね。どうやって使えばいいんだ、こんな欠陥品。
社員の誰からも意見が出なかったんでしょうか。
社員といえば、10年ほど前に春陽堂に「何々というタイトルの文庫が文庫巻末の目録に載っているが、注文すればまだ買えるのか?」という質問の電話をしたところ「判りません」という返事。「誰か判る人はいるのか?」には、しばらく考えた後「……いません」
こんな出版社ちょっとないっす。
をもらったことがあります。を
古本まゆさん
少年物は油断が出来ませんよね。カバーも中身も綺麗なのに、カバーを外したら表紙全面ボールペンによる物凄い落書き、と言うのを持っています。目録で買ったのですが、そこには表記がありませんでしたし、気づいたのがずいぶん後だったので、クレームもつけられませんでした。
まぁ、あまりにも美本な少年物も、それはそれでしっくりきませんが。
といったところで、昭和37年版の「江戸川乱歩名作集」は下記のような感じです。■は典拠で、手許にある版を掲げています。▼は依拠目録で、手許の典拠との異同はカッコ内に示してあります。いろいろ変なところがあるのですが、最高に変なのは4の書名で、『D坂の殺人』となっています。5の『人間椅子』も負けてはいません。初版発行が昭和34年とされていて、しかもこの一冊だけが『春陽堂書店発行図書総目録』に記載されていません。ついでに記しておきますと、この目録では下記の春陽文庫、「江戸川乱歩名作集」というシリーズ名は附されておりません。
江戸川乱歩名作集1 陰獣
昭和三十七年九月二十日 春陽文庫1073
カバー 一九一頁 八〇円
■第六十六刷(昭和五十一年一月三十日、二四〇円)
▼春陽堂書店発行図書総目録(一六七頁)
江戸川乱歩名作集2 パノラマ島奇談
昭和三十七年九月十五日 春陽文庫1068
カバー 二二一頁 九〇円
■第六十三刷(昭和五十一年十月十五日、二六〇円)
▼春陽堂書店発行図書総目録(二〇一頁)
江戸川乱歩名作集3 屋根裏の散歩者
昭和三十七年三月三十日 春陽文庫1097
カバー 二一四頁 一〇〇円
■第五十一刷(昭和四十九年四月三十日、二〇〇円)
▼春陽堂書店発行図書総目録
江戸川乱歩名作集4 D坂の殺人
昭和三十七年一月三十日 春陽文庫1098
カバー 二一四頁 一〇〇円
■第六十二刷(昭和四十九年五月十日、二〇〇円)
▼春陽堂書店発行図書総目録(D坂の殺人事件)
江戸川乱歩名作集5 人間椅子
昭和三十四年四月三十日 春陽文庫1023
カバー 二一七頁 ■円
■第四十三刷(昭和四十八年四月十五日、二〇〇円)
江戸川乱歩名作集6 月と手袋
昭和三十七年五月三十日 春陽文庫1231
カバー 二一七頁 一〇〇円
■第四十八刷(昭和四十九年五月十日、二〇〇円)
▼春陽堂書店発行図書総目録
江戸川乱歩名作集7 心理試験
昭和三十七年三月三十日 春陽文庫1106
カバー 二一三頁 一〇〇円
■第三十刷(昭和四十七年五月二十日、一四〇円)
▼春陽堂書店発行図書総目録
先日書き込みました昭和44年版のデータは、『春陽堂書店発行図書総目録』から拾ったものです。講談社の江戸川乱歩推理小説文庫に収録された乱歩の著書目録にも、この昭和44年版のことは記されています。だから出ることは出たのではないかと思うのですが、いまだに実見の機会を得ません。
春陽堂よ、大丈夫かね。
■喜国雅彦様
といったような次第です。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
■やよい様
昨日は失礼しました。いつもご親切にありがとうございます。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
■金光寛峯様
「豚と薔薇」のご報告、ご苦労様でした。司馬遼太郎の推理小説観は、私にはたいそう面白いものです。私はこれまで、おまえはどうしてミステリー小説を読まないのかと尋ねられるたびに(いや私だって多少は読んでますけど)、三島由紀夫の探偵小説観を紹介して済ませることにしていたのですが、司馬遼太郎の推理小説観もつけ加えるべきかもしれません。「探偵たちの変質的な詮索癖」はたしかに気色の悪いものですし、さらにいえば、そうした探偵たちを好んで描きたがる探偵小説家もまた気色の悪い存在です。もっともお説のとおり、書誌調査に血眼になる手合いも似たり寄ったりですから負けず劣らず気色の悪い存在ではあり、私なんてまあこの気色の悪さゆえに世間から、とくに女の子からはどれだけ毛嫌いされていることか。
春陽堂よ、おまえは私だ。
きょうも二分割です。
■喜国雅彦様
昨日は失礼しました。お手数をおかけしました。春陽文庫で要らざるムカムカまでご経験なさいました由、ほんとに申し訳ありません。春陽文庫に関しては、私もなかば以上諦めております。しかし喜国さんから、悪いことはいわない、なかったことにしよう、などとおっしゃられました日には、私はなんですかいきなり別れ話を切り出されてしまった女の子のような気分です。
●春陽文庫の謎
春陽文庫は変です。ほんとに変です。何から何までほんとに変で、わからないことだらけです。春陽堂からは『春陽堂書店発行図書総目録(1879年〜1988年)』(1991年刊、八〇〇〇円)というのが出ていて、私は今年の春この目録の存在を知り、さっそく購入いたしました。しかし、これはさぞ重宝するだろうなという期待はあっさり裏切られ、春陽文庫はほんとに変だという印象をいよいよ強める結果となりました。
この目録巻頭の「序文」および「編集にあたって」によれば、春陽堂は関東大震災と太平洋戦争とで被災し、「ほとんどの書籍および文献資料を焼失」したため、目録作成には「当社以外の文献に頼らざるをえ」なかったとのことです。こーんな言い訳が通用すると思ってるのか、と私は思います。太平洋戦争ですべての書籍を失ったとしても、目録のほぼ半分を占めるのは戦後の発行物ですから、戦後分の不備を震災や戦災のせいにすることはできません。
むろん同社に、戦後の自社出版物のすべてが保存されているとは限らないでしょう。しかし驚くべきことに、現在流通している春陽文庫の「江戸川乱歩文庫」、多賀新さんのカバー画でおなじみのあの文庫本のデータをこの目録で調べてみると、全三十冊のうち十六冊のデータに誤記が見られます。これはいったいどうしたことか。春陽堂よ、大丈夫かね。
ほかにも春陽文庫に関しては疑問が山積しているのですが、先述のごとく私はすでにほぼ匙を投げております。ドクター・スロー・ザ・スプーン、ってやつですか。こうなるまでに私はさまざまな辛酸を舐めつくし、春陽文庫の奥付をひっくりかえして驚いたり呆れたり泣いたり怒ったり喚いたり叫んだりいろいろなことを経験してきたわけですが、最終的に実感されたのはある種の気色の悪さでした。この気色悪さは、おそらく了解不能性に発しているのだろうと思われます。
春陽堂はいったい何を考えているのだろう。どんな目的があってこんな無茶苦茶な奥付をつくっているのだろう。
それがまったくわかりません。狂人を相手にしているような了解不能性が惻々と迫ってきます。
たとえば先日も記しましたとおり、光文社の少年探偵江戸川乱歩全集の初期六冊には奥付上にしか存在しない幻の初版があるのですが、この奥付の操作は全集としての統一性に対する配慮からなされたのだろうなとは推察されます。つまり操作の理由を推測了解することが可能なのですが、春陽文庫の奥付にはそれがありません。まったくありません。春陽堂よ、大丈夫かね。
『豚と薔薇』(司馬遼太郎, 1960.11.1, 東方社, \250)
表題作と「兜卒天の巡礼」の二篇を収録。205頁、函付。装丁真鍋博。
ソフトカバー版も出ているらしい(未見)。作品集や全集等へ再録されたことは
ない。表題作が著者唯一(?)の推理小説。1960年「週刊文春」に数回連載。
司馬に詳しい人によれば、『古寺炎上』(1962, 角川小説新書)も金閣寺炎上を
題材にした推理小説だとか。未見。
*
ヒロインは三十を過ぎようとしている年の、地味な事務員を務める独身一人暮らし
の田尻志津子。
"口紅をつける程度で、化粧もほとんどしたことがなかったが、やや厚手で
無表情な顔が、男の中年の食欲にふしぎな魅力をそそるようであった"
なにかと嫌なことが続いてくさくさしていたので、休暇を取って気晴らししようと
したとたん虫垂炎に罹って、それがすっかりこじれて二ヶ月も棒に振っていた。
不意に刑事の来訪を受け、尾沼幸治の変死を知らされたのはそんな折の事だった。
肉体関係だけの男だった。志津子宛の葉書だけを残して、死んだ。名前より他は何も
語らず、聞こうともしなかった相手だというのに、志津子は事件を探ることを決める。
"自分の一生の中で、一番愚劣なことをいま、しに行くの" と志津子。
−まだ愛しているのか
"そのときでさえも愛したことがないのに、いま愛しているはずがない"
−なぜ今さら、愛していない死人の身辺を詮索するのか
"自分でもよくわからないわ。そのときは、相手を知りたくはないし、
自分も知られたくはなかった。だけど、相手が死んだ今となってみれ
ば、相手についての知識が零では落ちつかなくなってきた。五ヶ月だっ
たけど、その期間だけ自分の人生が空白になっているような気がして
きたの"
−感傷だな
"ちがう。知識欲。−いや、あたしは利己主義者だから、自分自身の経歴
だけのために、そのファイルを整備しておきたいの。これ、悪趣味で言っ
ているんじゃない。この事件がもし他殺ならその犯人までつきとめたい。
自分自身の経歴のために−"
−意識過剰だ。感傷にすぎまい。
なんとかサスペンス劇場だののタイトルが頭をよぎる展開、おもわず「聖母たちの
ララバイ」でも口ずさみたくなってきますが、それほど品下ったしろものでもあり
ません。
さて、本作「豚と薔薇」がすこしでもミステリファンに知られているとすれば、それ
は故瀬戸川猛資『夢想の研究 活字と映像の想像力』(1999.7.30, 創元ライブラリ)
所収の「ビデオ雑記帳から」における言及によるものでしょう。みじかいものですが
簡にして要をえた、著者の洞察のするどさをじゅうぶん堪能させる文章であります。
以降の紹介も本論に沿っておこなうのが一番よいでしょう。
いわく、世の中には作者に嫌悪される作品というものが存在する。ビリー・ワイル
ダーが映画「情婦」を「反吐が出るほどイヤだ」と罵倒したように。そこには厭う
べき、他人には容易に窺いしれぬ何かが存在する、が、本作での司馬は単純。それ
がミステリだからである。
あとがきで作者の司馬はこう切ってすてる。
"私は、推理小説にはほとんど興味をもっておらず、才能もなく、知識も
ない。書けといわれて、ようやく書いた。むろん、推理小説というもの
はこれ一作で、生涯書くまいとおもっている"
こんな風変わりなおもしろい<あとがき>を読んだことがない、と瀬戸川は述べ、
ついで以下の文を引いて「つくづくと司馬遼太郎の観察眼の鋭さを感じさせる」
と唸ってみせます。
"私は、推理小説に登場してくる探偵役を(ママ)、決して好きではない。
他人の秘事を、なぜあれほどの執拗さであばきたてねばならないのか、
その情熱の根源がわからない"
探偵よ、お前たち自身が《謎》なのだ! であれば、司馬はヒロインにくだくだしい
ほどに動機を語らせもするし、また、
"それらの探偵たちの変質的な詮索癖こそ、小説のテーマであり、もし
くは、精神病学の研究対象ではないかとさえおもっている"
と指摘します。さらに、
"そういう疑問が、私という小説読者を推理小説に近づけなかったことで
もあるし、(中略) ついに、テーマを犯罪のナゾ解きに置くことを怠り、
他のことに重心をおいた。当然、作品のぬえのようなものになった"
と降りかえっています。
瀬戸川の筆は映画「シャーロック・ホームズの素敵な挑戦」にすすみますが、
(名探偵ホームズと少壮気鋭の医師フロイトが面と向かい合い、精神分析によって
探偵の心の中が探偵される物語) ここは本作のほうの話をつづけます。
作品はヒロインの兄の友人である新聞記者が登場し、一つ一つ手がかりを手繰りよせ
ては、尾沼の来歴や関わりのあった人物などをさぐりだし、また一つずつ犯人の可能
性をつぶしてゆく、足でかせぐ型の筋になっています。個人的にはこうした骨格は嫌
いではありません。たとえば書誌調査なども古書店や図書館などを廻り、やれあの文
献を当たらねば、やれあの件は調べておかねば、やれ総目次を洗い直さねば、と Todo
リストを書き連ねては一件々々消してゆく繰り返しでありましょう。親近感みたいな
ものを感じるのです。
さすがに肉付けはたっしゃなもので、公権力の裏づけもなにもなく、ぶしつけに尋ね
ていった自分たちがいかにして人名簿の類を出させて調べるのか、そうした細部に作
者 (元新聞記者) の経験をうかがわせます。「縁談のための調査だ」といってまんま
と学校職員をごまかして名簿を出させるあたりなど、時代背景もうかがわせて興味深
いものがあります。今ではこんな手は通用しないでしょうね、たぶん。
作者のいうとおり、ロジックで犯人を追いつめてゆく本格の知的興味はいまいちです
が、一度は (アンソロジー等への収録なり) 陽の目をみてもよいのではないかという
のが率直なところであります。
頼まれて、庭の草刈、奇妙な草花が多いです。
河出文庫『飛鳥高名作選 犯罪の場』日下三蔵編、購入。
短編67編(「推理小説研究11号」より)もあるのですね。
第2期が望まれます。
私は意外と読んでいないことがわかりました。
意外と調べたり、見たりしていますと、このような時に限り、落丁に目がいき、気になりますね。しかし、もう、見ていないことにして、考えないことにしています。
今年、「SFマガジン」の後半に、落丁があるのに、購入。ないものも、購入。
喜国雅彦さま
古本には、どうしてもそうしたリスクが付きまといます。古本屋としても高い本は落丁・乱丁まで調べているのですが、全ての本にはとても手がまわりません。
先日の名古屋の市で、甲賀三郎の少年物の貴重な本を落札したつもりだったのですが、店に帰って調べてみると非道い乱丁があって、本当にがっかりしています。
やよいさま
いや〜っ、懐かしい。「日本暗号協会」の名前が出てくるとは。とは言っても、無期限のお休みに入っているだけで、解散したとは聞いていないのですが。
暗号協会の活動は、僕の今までの人生の中におけるもっとも楽しい想い出です。勿論、会員証や会誌・暗号も、宝物として大事に保存しております。
あの頃はまだ、古本屋というヤクザな仕事をすることになるとは思ってもいなかったのですが、どうも今振り返ってみると、日本暗号協会→古本屋、という道筋ができあがっていたような気がしない訳でもありません。
あの頃遭った人たちも、それぞれの分野でご活躍のことでしょうね。ひょっとしてこのボードに書き込んでいる方なら、会員の方もみえるのでは?
■喜国雅彦様、やよい様
おはようございます。ありがとうございます。また明朝、あらためてご挨拶を申しあげます。きょうはいけません。二日酔いです。どーもすいませんです。いざさらば。
中さま
同書は、日本暗号協会設立に先駆け刊行された文庫オリジナル版のようです。
(中島河太郎の序文)
とりいそぎ
まず春陽文庫の『江戸川乱歩名作集』を調べましたが、変なことになっています。
中さんのリストではこれらの初版は昭和44年になっていますが、僕所有の後の版では「昭和37年」になっています。ははーーん、これは「名作集」が付かないころの元版の初版を表記しているのだな、とそれらを調べる。すると、元版の初版は「昭和27年」。ありゃりゃ? しかも僕の本は「昭和39年 7刷り」。春陽堂の表記のみを信用すれば『昭和37年には「元版」と「名作集」の2種の文庫を売っていたことになります。これはどう考えてもおかしい。中さんの調べた昭和44年が正しいのなら、これは解決です。ならばなぜ「初版37年」などと嘘の表記をしているのでしょう。
結論「もう金輪際、春陽堂の出版物の初版は調べません(笑)」 だから中さんも悪いことはいいません。「春陽文庫はすべてなかったこと」にしませんか?
しかも調べていて、乱丁落丁を発見してムカムカしましたし(怒)、
平成になってからの出版物にも乱丁落丁があるところがスゴイぞ春陽堂。
次、函版光文社全集です。
以前アップされていたのは次のとおりですが
怪人二十面相 少年探偵団全集1
昭和三十六年十二月十日
B6判 函 二二八頁 二五〇円
装丁:白井哲 さしえ:武部本一郎
少年探偵団 少年探偵団全集2
昭和三十六年十二月十日
B6判 函 二一〇頁 二五〇円
装丁:白井哲 さしえ:武部本一郎
妖怪博士 少年探偵団全集3
昭和三十六年十二月十五日
B6判 函 二二一頁 二五〇円
装丁:白井哲 さしえ:武部本一郎
大金塊 少年探偵団全集4
昭和三十六年十二月十五日
B6判 函 二一三頁 二五〇円
装丁:白井哲 さしえ:武部本一郎
青銅の魔人 少年探偵団全集5
昭和三十六年十二月二十日
B6判 函 一八六頁 二五〇円
装丁:白井哲 さしえ:武部本一郎
妖怪博士のページ数が違っていました。正しくは「224」です。あとは間違いありません。
そんで「少年探偵団ニュース」ですが、「NO2」のみ所持しています。紙ぺら3枚の全12ページ
タイトルのみ書きます。ちなみにページ数はふってないので「実は全320ページ」かもしれません。
1 「お正月までに5さつそろう」
2〜3 「坂本九ちゃんも愛読者です」 「知っていますか? 少年探偵団七つのクイズ」
4〜5 「秘密インキ(あぶりだし)の作り方
6 「テレビよりずっといきいき(波多野完治)」
7 「私も少年探偵団のファン!(手塚治虫)」
8 「忍術使いの暗号(七字の仮名)」
9 「私も乱歩先生の本がおもしろく、それから推理小説をかきはじめた(松本清張)」
10〜11 「諸君もつかえるボーイスカウトの絵文字」
12 「おめでとう江戸川乱歩先生(小林芳雄)」
おっと小林少年はこんなところで文章も書いていたのか。締めの言葉は持ち芸の「江戸川乱歩先生バンザーイ」です。あとの3冊にも「ニュース」が付いていたかは不明。
つぎ、所持本です
江戸川乱歩 現代長編全集5
【発行日】昭和四十三年十二月六日第一刷発行
【体裁】B6 函 414P 著者写真 カラーイラスト口絵
【発行所】講談社
【収録】陰獣・一寸法師・孤島の鬼・黒蜥蜴
【装幀】原 弘
【月報?】不明
屋根裏の散歩者 D坂の殺人事件
【発行日】平成八年三月十五日発行
【体裁】93P
【発行所】新潮社 新潮ピコ文庫
現代怪奇小説集 上
【発行日】昭和五十二年四月十五日 第一刷
【発行所】立風書房
【体裁】B6判 カバー
【編】中島河太郎、紀田順一郎
【収録】人でなしの恋(47〜65P)
以上。「貸本小説」買いに都心に行かなきゃ。
http://plaza22.mbn.or.jp/~kunikikuni/kikuni/kikuni.html
■やよい様
どうもありがとうございました。この『ワンダー暗号ランド パズルつき・暗号推理小説傑作選』は、いわゆる文庫オリジナルの刊行なのでしょうか。何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
■末永昭二様
ご高著大好評発売中の由、お慶び申しあげます。残念ながら当地の本屋ではやはり見かけません。インターネット書店に注文すればいいようなものですが、私はいまだにあれに馴染めず、本は本屋さんでゆっくり本を眺めながら買いたいものだと思っております。近く大阪で購入いたします。
雑誌グラビアの件、何かと気にかけていただいて感謝いたします。左幸子とかあのあたりでしょうか。楽しみにしております。
「変色までを造本と考えました」とのお言葉、たいへん興味深いものです。じつは名張市立図書館の『江戸川乱歩執筆年譜』も、表紙をよく見るとあちこちにシミが発見できます。装幀担当の戸田勝久さんによりますと、わざとシミのある紙を選んで原画を描いたとのことで、新刊にして古書の趣が味わえる一冊となっております。と話の流れがいささか強引なのですが──
●戸田勝久絵画展─蕪村幻影として─
その戸田さんが9月2日から30日まで、東京で個展を開催していらっしゃいます。神戸在住の戸田さんにとって、東京では初めての個展です。会場は、今年1月から2月にかけて渡辺啓助さんの個展が開かれた書肆啓祐堂。詳細は下記のホームページでご覧ください。
書肆啓祐堂
http://www.keiyudoh.com/
戸田さんは昨年、おうふうから出た『蕪村全句集』の装幀を担当されましたので、今度の個展はそれにちなんだテーマのようです。どうぞお立ち寄りください。
●乱歩著書目録アンソロジー篇
乱歩が死去した昭和40年から今年までを対象に、乱歩作品が収録されたアンソロジーのリストをつくりました。ご覧いただいて不備をご指摘いただくためのものです。
江戸川乱歩アンソロジーリストβ版平成篇
http://www.e-net.or.jp/user/stako/list-anthology1.html
江戸川乱歩アンソロジーリストβ版昭和歿後篇
http://www.e-net.or.jp/user/stako/list-anthology2.html
ぜひ一度ご高覧ください。
「小林文庫」の、江戸川乱歩賞。昭和44年の項。気になる候補作であげられた、「寒い鉱山から」。これは「北の廃杭」に改稿・改題されたようです。角川文庫「俘虜偽装殺人事件 明日知れぬ命」草野唯雄、h12.1.10初版、解説 山前譲、より。
東海次郎の『殺すのはいやだ』初版、昭和21.9.15、民生書院、を入手。
再版(昭和22.5.30)はすでに入手していましたが。
同じ著者で、『国際武器密売団』昭和23.11.30発行、民生書院も同時に入手。同じ発行所でしたが、住所ちがい。
しかし、内容は、『殺すのはいやだ』と同一。
上記の初版、再版を上下・左をそれぞれ五ミリ裁断したものでした。
『貸本小説』をお買い上げの皆さま、本当にありがとうございます。
大型書店を覗いたら20冊近く平積みになっていて、何か恐ろしい気がして、そそくさと店を出てしまったという小心な私です。
本日は、表紙を描いていただいた堂昌一画伯に、本を持ってご挨拶に。
すぐに意図をおわかりいただいたようで、なかなかウケていました。
書影をご覧になって、「懐かしいなあ」とのこと。よかった。一安心です。
その後、日経新聞で著者インタビュー。1時間くらい話して来ました。
9月16日の読書欄に掲載される予定です。
須川様。
その本は「持っているうちに時代が付く」ので、だれも変色を止めることはできません。変色までを造本と考えました。でも、昔の酸性紙のようにぼろぼろになってしまうことはないとのことなので、どうぞご安心を。
中様。
乱歩関係で、ちょっと面白いものを買いました。雑誌のグラビアでひいきの女優さんを開陳する、といったタグイをいくつかまとめて。
彩古さん同様、私も乱歩は守備範囲ではないので、こんなことでご協力できればと思います。
桜様。
ありがとうございます。
これが売れれば続編もできるかと思いますので、ともかく今は宣伝に専念したいと思います。
リストについては、今のところ考えていません(多分将来的にも)。というのは、貸本小説については定義がまったくあいまいなことと、これから何年がんばっても、私の能力では、「ある程度全体を見渡す」ことすら無理だと思われるからです。リストが何かの意味を持つかというのも、正直なところ疑問ですし(作ったとしても、現物が入手しにくいので誰も利用できないものになりそうですから)。
ワンダー暗号ランド−パズルつき・暗号推理小説傑作選
【発行日】昭和六十一年七月十五日 第一刷発行
【発行所】講談社/講談社文庫
【編】長田順行
【収録】黒手組
現物で確認いたしました。長田氏の解説では「暗号記法の分類」、「二銭銅貨」、「恋二題」、「孤島の鬼」、「黄金仮面」が紹介されています。
ようやく火曜日に入手し一気に読みました。
面白い! 装丁もなかなか配慮の行き届いた
もので感動。紙質の選定に意を払ったあたりは
笑っちゃいました(~o~)
しかしこの本の保存はどうしたものか・・?
■彩古様
はじめまして。お知らせありがとうございます。
乱歩の書簡発見の記事、当地の朝日新聞にはけさ掲載されております。見出しは、
《「種だけじゃ…」探偵小説の志/江戸川乱歩から横溝正史へ/手紙35通 戦争から解放された情熱》
といった感じですが、asahi.com の「乱歩、横溝あてに探偵小説論 大量の手紙の写し」に比べると(ということは、東京本社発行の朝日に比べると、ということになるのでしょうか。ちなみに当地の朝日は名古屋本社発行です)若干省略があるようで、「弓弦城殺人事件」や「幻の女」に関するエピソードなどは割愛されています。
Mainichi Interactive には、「土蔵から乱歩の手紙」という記事が掲載されています。アドレスは下記のとおりです。
http://www.mainichi.co.jp/news/journal/photojournal/
それにしても、乱歩邸の土蔵を本気になってひっかき回せば、とんでもない発見がまだいくらでも出てくるのではないでしょうか。打ち首獄門は覚悟の上で、土蔵破りになりたい気分。
それからあの、乱歩の著書をさほどお持ちでないからといって、別にお謝りいただかねばならぬ訳合いは少しもありません。じつはかく申す私とて、講談社の江戸川乱歩推理文庫が完結したとき乱歩の本はこれでいいやと思い、角川文庫の乱歩の著作やばらばらで持っていた講談社の二十五巻本全集などをすべて処分してしまった口です。その後なんだか妙ななりゆきで名張市立図書館カリスマ嘱託ということになってしまいましたので、いまでは講談社の十五巻本全集も自宅にちゃんと揃えておりますが、じつはこの全集十五巻、名張市立図書館の地下書庫の片隅で埃をかぶっていたダブり本のなかからこそこそ持ち帰ったものです。もしかしたらこれは犯罪なのかもしれません。どうかご内聞に願います。
■平山雄一様
「しょうそう文学研究所」の件、了解しました。当方のページのリンク、近く設定し直します。
■ iizuka 様
毎度ありがとうございます。講談社文庫だと、奥付の表記は「第一刷」でしょうか。
これまでは気にもとめていなかったのですが、初版を意味する言葉にもいくつかあって、たとえば新潮社は初版、講談社は第一刷、光文社は初版一刷(昭和52年あたりまでは初版だけでした)を使用しています。珍しいところでは初刷、なんてのもありますが、さすがに初体験、などというふざけたものは見当たりません。
『透明人間大パーティ』のデータ、下記のとおりといたします。
透明人間大パーティ
【発行日】昭和六十年七月十五日
【発行所】講談社/講談社文庫
【編】鮎川哲也
【収録】透明の恐怖
【典拠】●第一刷(iizuka)
また何かのおりにはよろしくお願いいたします。
●乱歩著書目録アンソロジー篇
本日も文庫本です。
ワンダー暗号ランド
昭和六十一年七月十五日 講談社/講談社文庫
奇妙なはなし
平成五年■月■日 文藝春秋/文春文庫
平成5年といえばついこのあいだなのですが。
末永さんの『貸本小説』、横田さんの偉業を思い出させます。さらに、続刊がかかれることを望みます。
栗田信さんのを所有するのは一冊ですが、他のも探したくなります。とくに、カッポウ先生とケロリン娘のシリーズ(?)も読みたくなります。「人名・作品名さくいん」がありますので、次回は、それぞれの著者の作品リストが欲しいように思います。
それぞれの作家、どのくらいの作品が貸本としてのみ、製作されたのでしょうか。興味が尽きません。
彩古さんが書かれた乱歩の書簡、今日の朝のテレビの話題でした。
横溝さん宛のが保管されているのであれば、横溝さん宛以外にも、さらにあることを意味しているのではないか、と思われます。
司馬遼太郎唯一のミステリ『豚と薔薇』、なにげにグーグルで検索してみたら…
なんだ、あるじゃないですか。さっそく注文。ぶじ買えたならば、そうですね
"ちょいめずを読む・出張版" と称してここでレビューしてみましょうか、って
人の企画じゃねーかよパクんじゃねーよオイ>おれ ;-p
中相作 様
講談社文庫の『透明人間大パーティ』持っていました。
【発行日】昭和六十年七月十五日
【発行所】講談社
【編】鮎川哲也
【収録】透明の恐怖(エッセイ)
です。
巻末の解説は鮎川哲也さんと新保博久さんが分担しており、
「透明の恐怖」については新保さんが書いています。
今日は、平山雄一です。
Shoso-in Bulletin日本語版のページのほうを、
しょうそう文学研究所
http://page.freett.com/Shoso/index.htm
と名前をつけて、新しいプロバイダに移動しました。
asahi.comで江戸川乱歩の書簡の写しが大量に発見されたというニュースが
流れていますので、お知らせします。16時過ぎの第一報ですね。
明日の朝刊にも掲載されるのでしょうか。
http://www.asahi.com/culture/update/0905/003.html
乱歩書誌に関しては中さんにほとんど協力できないことが残念です。
マイナーな作家に対しての興味が強いので、乱歩と横溝は後回しに
なってしまうのでした。研究されている方はたくさんおりますし。
乱歩は講談社文庫があればよいやと、異装本や元本をほとんど
持っておりません。
申し訳ありません。
■森英俊様
さっそくのお知らせ、ありがとうございます。「江戸川乱歩氏推奨」とあるだけでも、当方にとってはたいへん貴重なデータです。今後ともよろしくお願いいたします。
■喜国雅彦様
お忙しいところ、ありがとうございます。「江戸川乱歩(カセットブック)」のページ、以前にも拝見したことがあるのですが、失念しておりました。カセットブックそれぞれの短評も面白く拝読いたしました。私はやはり白石加代子さんを一押ししたいと思います。
『探偵作家江戸川乱歩の事件簿 ミイラと旅する男』は、きのうの新聞に同書の広告が出ていて、よく見ると「新書判」とありましたので、
「あ」
と思いました。てっきりハードカバーだと思い込んでいた次第です。
そういえば私は、新書判のいわゆるノベルスというものをあまりといいますかほとんどといいますかまずめったに読みませんので、本屋さんに入ってもいわゆるノベルスの棚は素通りしがちです。
で昨日、伊賀地域最大の新刊書店「ブックス・アルデ」に赴き、いわゆるノベルスのコーナーを探しますと、『探偵作家江戸川乱歩の事件簿 ミイラと旅する男』が一冊だけ平積みになっておりました。購入しました。まだ拝読はしていないのですが、巻末の「おもな参考資料」に名張市立図書館の『乱歩文献データブック』をリストアップしていただいてありましたので、妙ににこにこしてしまいました。
さて仰せのとおり、小説の「文章」はやはりとても気になるものです。私が上述のごとくいわゆるノベルス一般をあまり読まぬのはいわゆるノベルスに対する拭いがたい偏見があるからで、それはひとことでいえば、へったくそな文章でたらたらたらたらと説明だけをえんえん書き連ねたしろものを小説と称して売っているのではないかという偏見です。偏見です偏見です。ほとんど根拠のない偏見ですからノベルスの売り手や書き手や読み手の諸兄姉はそんなに目くじらをお立てになりませぬように。ええごめんなさい。
ミステリーファンのみなさんなら、トリックへの期待を優先させて劣悪な文章には眼をつむるということも可能なのでしょうが、私はミステリーファンではありませんので、こんな文章を読まされるのはいやだいやだと思ったらその時点で投げ出してしまいます。ええごめんなさい。
しかし『探偵作家江戸川乱歩の事件簿 ミイラと旅する男』は、なにしろ最新の“乱歩小説”ですから、最後まで拝読したいと思っております。
えー、ミステリーファンのみなさんがお集まりになる掲示板でなんとも口幅ったいことを申しあげてしまいました。ええごめんなさい。
■アイナット様
目一杯お手数をおかけしております。おおいに助かっております。復刻版二冊の書誌データ、完璧にわかりました。乗りかけた船です。残りの号もなにとぞよろしくお願い申しあげます。
■フク様
ご無沙汰いたしました。『恐怖館 残酷ミステリー集』、おかげさまで必要なデータがすべて把握できました。下記のとおりとなります。
恐怖館 残酷ミステリー集
【発行日】昭和五十一年十月五日
【発行所】青樹社
【編】山村正夫
【収録】芋虫
【典拠】●初版(フク)
ご所蔵の山田風太郎『女人国伝奇』は、昭和39年8月発行のものでしょうか。それならコピーをもっておりますので、ご放念ください。ほかにもまだ何か、お気づきのことがおありでしたらよろしくご教示をお願いします。
■かわぐち@白梅軒様
はじめまして。ご親切にありがとうございます。『残酷な戦慄』、こんな感じでよろしいでしょうか。
残酷な戦慄
【発行日】昭和五十二年四月三十日
【発行所】青樹社
【編】山村正夫
【収録】目羅博士
【典拠】●初版(かわぐち@白梅軒)
今後ともよろしくお願いいたします。
●乱歩著書目録アンソロジー篇
本日は下記の一冊です。
透明人間大パーティ
昭和六十年■月■日
昭和60年に出た本のこともわからぬのですから、じつにお恥ずかしいかぎりです。
PR誌「本の旅人」九月号、2001。「田中潤司&北村薫&有栖川有栖 本格ミステリの新時代」は、角川文庫と内容的には同一であることがわかります。順序が入れ替わっていますが、こちらのPR誌のほうが座談会の雰囲気をつたえていました。
図録では、最近、以下の2冊を入手。
・「2001年シネマ・オデッセイー映画ポスターの20世紀展図録」印刷博物館、文京区、1890円
・「真鍋博回顧展 イマジネーションの散歩道」愛媛県美術館、2200円
下に書きました、東 震太郎さんの本では、山前譲編の書誌では、『七色真珠』、昭和22年、4.1、(青い壜、とかげクラブ)が1点、書かれていました。雑誌では、昭和22から24年に、探偵小説が掲載されています。これらが先の短編集に収録されているのでしょうか。
おずおずとこんな晴れがましい舞台に顔を出してみました。
『残酷な戦慄』(青樹社)
発行日は昭和52年4月30日と記されております。
| Powered by T-Note Ver.3.20 |