|
久し振りに落語の寄席を聞く機会がありました。落語好きな次男が手配してくれた東西名人寄席と銘打った歌丸、
文珍と小朝各師匠による古典・創作落語は楽しいものでした。寄席と言っても大きなホールでの地方公演ですから、
噺家のほうも小さな演芸場とは勝手が違っただろうと思いますが、
話の展開とオチに日本語の機微を織り込んで人を笑わせるという「話芸」に感心して聞き入っていました。
 江戸期に始まり文化・文政年間に大いに発展したと伝えられる落語は、江戸時代の言葉づかいを今に伝える貴重な媒体でもあります。
江戸時代の町人たちの闊達としたしゃべり方を今に伝えます。世界的に見ても三百年ほど前の言葉を聞けるのは珍しいと言われる所以です。
江戸期に始まり文化・文政年間に大いに発展したと伝えられる落語は、江戸時代の言葉づかいを今に伝える貴重な媒体でもあります。
江戸時代の町人たちの闊達としたしゃべり方を今に伝えます。世界的に見ても三百年ほど前の言葉を聞けるのは珍しいと言われる所以です。
実際に江戸時代の町民はどんな話し方をしていたのか、古典にある「大工調べ」から少し長くなりますが拾ってみます。出典は五代目志ん生。
【実におもしろいもんで、朝晩つきあう人のなまえもほんとに知らないで、そしてつきあってんですからな。
「少々伺いますけれど」
「何だ、何だ」
「このへんにヤマダキサブローさんって方、おりましょーかねー」
「何おー、ヤマダキサブロー、おそろしいなげーなめーだなー。しょーべーは、何だ?」
「商売は大工さんですが」
「でーくでヤマダキサブローだと? でーくのヤマダキサブローなんてのはー、なー…、キサコー」
「お!」
「でーくでヤマダキサブローってのを知ってるか、おめー」
「でーくでヤマダキサブローってのは、・・・・・おれだ」
「何を言ってやんだい。てめー、でーくのキサッペってんじゃねーかーよー」
「それが、おれヤマダなんだよ」
「ヤマダってつらじゃーねーよー、てめーは。じゃまだってつらだ」
(別の大工仲間に向かって)
「おめー、なにかい、キサッペのなまえ知ってるかよ」
「知ってるわな。でーくのキサッペだろ」
「でーくのキサッペじゃーねーやい」
「そーかー?」
「おれも大工のキサッペだとばっか思ってた。したところが、そうじゃねーんだ」
「ふーん」
「大工のキサッペってゆーのは、浮世を忍ぶ仮の名だ。まこと本名は、ヤマダキサブローてんだとよ」
「へー、ふてーやろーだ」 】
子供の頃、近所の遊び仲間でこんな経験をしたことがあるような気がしますね。
○○ちゃん、って呼んでたのに正式な名前を知らないという感覚。
文章にしてしまうと大工さんの言葉使いが随分悪いように聞こえますが、今でも若い世代の仲間内で気を許して話しているときも似たり寄ったりの言葉使いです。
江戸弁の特徴でもある「エー」とのばすエ列長音は、江戸時代から現れた発音で現在に継承されたものですが、当時はもっと頻用していたようです。
ダイク→デーク、ショウバイ→ショーベー、ナガイ→ナゲーのようにaiと母音が続くとe:とエ列長音になります。
他にもナマエ→ナメーのようなaeがエーになったり、フトイ→フテーのようなoiがエーになるパターンがあります。
気短でキップがいいのが江戸人の特徴なので、言葉使いも上方とは違った端折り方をしたのかもしれず、母音を短く子音を強く発音することが多かったようです。
「スルッテートナニカイ」など母音が極端に短く感じますね。
もっとも江戸でもこういった「イテー」式のしゃべり方をしていたのは長屋暮らしの普通の町民たちで、
武士階級や大商人たちは丁寧に「ショウバイ」「イタイ」と言っていたようです。でも乱暴だけれども裏には人情がこもっている、
こういう言葉こそ江戸町民の好みだったのかもしれません。
見てくればかり気にしている人間とは一線を画しているという自負さえ感じられる威勢のいい発音となって今でも下町言葉に残って活躍しています。
明治の中頃までは書く文章と話す言葉は別物でした。文語体と口語体です。時代劇に見られるように話は普通の話し言葉ですが、
巻手紙になると「ござ候」式の裃を着たような武張った文章になってしまいます。明治の作家たちは言文一致の試みを模索します。
口火を切ったのは二葉亭四迷。坪内逍遥の「円朝の落語をまねて書いたら」の勧めで、あの初の言文一致体の小説「浮雲」を完成させます。
三遊亭円朝は明治落語界の中興の祖と言われた名人で、その速記録が残っており誰の心にも訴えかける素晴らしい語り口だったと伝えられています。
こうして見ると落語も笑いを取るだけでなく文学や一般庶民の国語力にも貢献して深く市井に浸透していたのが読み取れます。
「笑点」が放送50年を迎えてなお高視聴率を保っているのもむベなるかなです。
最後に好きな枕をひとつ。
「棟梁!棟梁!昨日作ってもらった棚なんですがね。もう壊れちゃいましたよー」
「壊れた?・・・・・おかしいなあー、・・・・…なんかものを載せやしませんでしたか?」
こんなとぼけた棟梁になれればいいですね。
|

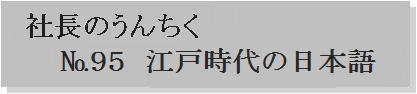
 江戸期に始まり文化・文政年間に大いに発展したと伝えられる落語は、江戸時代の言葉づかいを今に伝える貴重な媒体でもあります。
江戸時代の町人たちの闊達としたしゃべり方を今に伝えます。世界的に見ても三百年ほど前の言葉を聞けるのは珍しいと言われる所以です。
江戸期に始まり文化・文政年間に大いに発展したと伝えられる落語は、江戸時代の言葉づかいを今に伝える貴重な媒体でもあります。
江戸時代の町人たちの闊達としたしゃべり方を今に伝えます。世界的に見ても三百年ほど前の言葉を聞けるのは珍しいと言われる所以です。