|
ジャーナリストの立花隆さんが亡くなられたと報道で知りました。
すでに4月には亡くなられていたとのことで、ひそかに知られず逝ったことが立花さんらしいと思いつつも大きな知識人をなくした喪失感は否めません。
そのデビューは鮮烈でした。
文芸春秋1974年11月号に載った「田中角栄研究」によって現職の首相だった田中を退陣に追い込み多くの人の価値観や考え方を変えた点において記念碑的な論文でした。
当時大学1年生だった私も普段読むことのなかった文芸春秋を手に取り、その衝撃の余波をマスコミや論壇で感じ取っていました。一つひとつの内容はすでに記者なら既知のもので、
そんなの知っているよ、というあしらい方でしたが、 全体にまとまるとその人脈と金脈に関するすごい論考になったという感じだったようです。
以降「革マルvs中核」や「日本共産党の研究」「農協」など著者でなく本の題名で興味を覚えて読んだものが結果として立花さんだったということが多かった。
タブー視された分野にも切り込んで身の安全も脅かされたこともしばしばだったと聞きます。その中でも最も興味深かったのがやはり「脳死」に関する著作だったように思います。
80年代になって脳死移植の普及に伴った脳死判定について多くの議論がなされました。「脳死は人の死か」ということについて医学者、宗教家、
法律家を巻き込んで一大論争となったのです。当時脳死については分からないことがたくさんありました。
68年の札幌医大・和田教授の日本初の心臓移植がドナーの脳死についての判定をあいまいにしたままで移植に踏み切ったため殺人罪で告訴されたがために、
それ以降トラウマとなって日本では移植がタブー視され進んでいなかったこと、そもそも人工呼吸器という大掛かりな機械がない医院程度では「脳死状態」は起きえないこと、
脳死と植物状態の違いについての理解が進んでいないこと、これまで慣習としてきた三大兆候死—自発呼吸の停止・瞳孔の散大・心停止という死の判定に当てはまらないこと等々、
この立花本によって教えられたことは多かった。
その取材の範囲は驚くほど広く、
医学書や医学雑誌論文まで洋の東西を問わず読破し専門家とも専門用語を駆使して対話できるレベルまでいっていたことに舌を巻かれることしばしばでした。
認める・認めないのどちらに与することなく冷静にニュートラルに事実を整理し最も説得性のある解決方法を読者に提示・判断させるという書き方は印象的でした。
 その後の著作は脳から発展したものだったのでしょうか、脳科学へ発展しさらには臨死体験、宇宙体験者の帰還後の心的変化などへと移っていきました。
知的好奇心に際限がなく文系理系の垣根も越えて「サル学」や「核融合」、「ビッグバン」など多岐に広がっていきました。
通称「猫ビル」と呼ばれる立花さんの事務所にはこれまで読んできた蔵書が置かれているそうですが、ざっと3万冊といわれています。
3万冊を読んで100冊の本を書いたといわれます。下世話な計算をすると1冊を集中して6時間で読んだとして、
1日の内12時間を費やすとしても単純計算で41年かかることになります。しかし取材、執筆などの時間を考えるとそう簡単ではありません。 その後の著作は脳から発展したものだったのでしょうか、脳科学へ発展しさらには臨死体験、宇宙体験者の帰還後の心的変化などへと移っていきました。
知的好奇心に際限がなく文系理系の垣根も越えて「サル学」や「核融合」、「ビッグバン」など多岐に広がっていきました。
通称「猫ビル」と呼ばれる立花さんの事務所にはこれまで読んできた蔵書が置かれているそうですが、ざっと3万冊といわれています。
3万冊を読んで100冊の本を書いたといわれます。下世話な計算をすると1冊を集中して6時間で読んだとして、
1日の内12時間を費やすとしても単純計算で41年かかることになります。しかし取材、執筆などの時間を考えるとそう簡単ではありません。
かつて東大阪市にある司馬遼太郎記念館に行ったことがありますが、そこには4万冊という司馬さんの蔵書が安藤忠雄の設計で吹抜けの書棚に納められていました。それを見上げて人間って生涯これだけの本を読むことができるんだと、感嘆したことを思い出します。
よく立花さんは生物がカンブリア紀に多様化したことを「カンブリア爆発」と呼ばれることに因んで、
コンピューターによってITやネットが発達して人類にとってこれまでにない科学や技術の進展を遂げたここ50年ほどの期間を「知の爆発」と称していました。
そのため現在の医学部などの学生が覚えなければならない知識は戦前のそれと比して80倍になったと記したことがあります。
同じように医学に限らず多くの分野で専門知識が溢れおのずと高い専門性が求められて、
ひいては知識のタコツボ化が起きて専門外には興味や関心が至らないという状況が呈されつつあることに危惧の念を抱いていました。
それだけに横断的に各分野の知識を網羅し統合的なレビューの語れる人が失われたことが惜しまれます。
しかし晩年「100年経ったらきっと100年前の人たちはこんなことも分からなかったんだって言われていますよ」とも話していました。
「知の巨人」と言われた立花さんには今の知的レベルがそんな風に映っていたのでしょうか。
合掌
| 
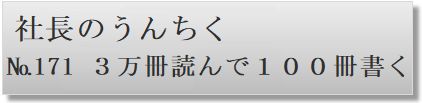
 その後の著作は脳から発展したものだったのでしょうか、脳科学へ発展しさらには臨死体験、宇宙体験者の帰還後の心的変化などへと移っていきました。
知的好奇心に際限がなく文系理系の垣根も越えて「サル学」や「核融合」、「ビッグバン」など多岐に広がっていきました。
通称「猫ビル」と呼ばれる立花さんの事務所にはこれまで読んできた蔵書が置かれているそうですが、ざっと3万冊といわれています。
3万冊を読んで100冊の本を書いたといわれます。下世話な計算をすると1冊を集中して6時間で読んだとして、
1日の内12時間を費やすとしても単純計算で41年かかることになります。しかし取材、執筆などの時間を考えるとそう簡単ではありません。
その後の著作は脳から発展したものだったのでしょうか、脳科学へ発展しさらには臨死体験、宇宙体験者の帰還後の心的変化などへと移っていきました。
知的好奇心に際限がなく文系理系の垣根も越えて「サル学」や「核融合」、「ビッグバン」など多岐に広がっていきました。
通称「猫ビル」と呼ばれる立花さんの事務所にはこれまで読んできた蔵書が置かれているそうですが、ざっと3万冊といわれています。
3万冊を読んで100冊の本を書いたといわれます。下世話な計算をすると1冊を集中して6時間で読んだとして、
1日の内12時間を費やすとしても単純計算で41年かかることになります。しかし取材、執筆などの時間を考えるとそう簡単ではありません。