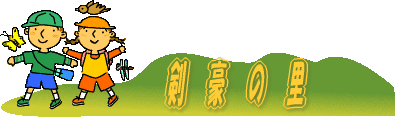
|
剣豪星野房吉先生追悼碑 碑文 |
|
寛政三年(一七九〇)勢多郡赤城村大字深山の名門須田家に生まる。諱は為信と称す。須田家の遠祖は元信濃国須坂の城主と伝え部門の家柄なり、祖父治右衛門は法神流の兵法者として知られ、父玄内は医を業とし画技に長ず。幼児より祖父に兵法を、父に医術を、さらに東里鳳斎、狩野探雲に師事して画技を、書を萩原賢和に学ぶ。天賦の才あり忽ちにしてその技量師を凌駕し神童の誉れあり。長ずるや躯幹長大力量抜群にして眉毛巻き上がり眼光炯々として偉丈夫の相あり。 |
![]()
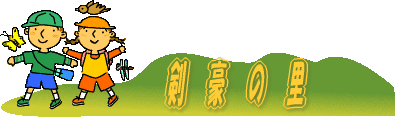
|
剣豪星野房吉先生追悼碑 碑文 |
|
寛政三年(一七九〇)勢多郡赤城村大字深山の名門須田家に生まる。諱は為信と称す。須田家の遠祖は元信濃国須坂の城主と伝え部門の家柄なり、祖父治右衛門は法神流の兵法者として知られ、父玄内は医を業とし画技に長ず。幼児より祖父に兵法を、父に医術を、さらに東里鳳斎、狩野探雲に師事して画技を、書を萩原賢和に学ぶ。天賦の才あり忽ちにしてその技量師を凌駕し神童の誉れあり。長ずるや躯幹長大力量抜群にして眉毛巻き上がり眼光炯々として偉丈夫の相あり。 |
![]()