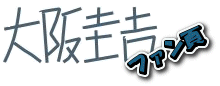
|
大阪圭吉の評価
|
|
江戸川乱歩
|
大阪君の作風は、ポオによって創始され、ドイルによって、更らに通俗化されながら、完成された所の、短編探偵小説の純粋正統を受継ぐものである。
(中略)併し、従来日本のどの作家が、かくまで純粋に、かくまで根強く、正統短編探偵小説への愛情と理解とを示し得たであろうか。
どの作家が、これ程深く理智探偵小説の骨法を体得し得たであろうか。
|
「序」(大阪圭吉著『死の快走船』1936年6月)
|
|
甲賀三郎
|
彼の作品はどの一つを取っても、ガッチリと組立てられている。短い枚数の中で、書くべき事をちゃんと書いている。
大体に於ては、弱々しく感ずるペエソスであるが、それがある故に彼の探偵小説には或る気品がある。
|
|
「大阪圭吉のユニクさ」(大阪圭吉著『死の快走船』1936年6月)
|
|
村山徳太郎
|
元来、本格作家の少ない吾国の探偵小説界とって大阪氏を失ったことは、少なからぬ損失である。
大阪氏の斯界にのこした足跡は小さいながら確実であった。いつまでも消えることなく、真面目な本格愛好者の記憶にこびりついて離れない
|
|
「大阪圭吉研究」(「黄色の部屋」1号 1949年10月)
|
|
鮎川哲也
|
大阪圭吉氏は、戦前を代表する本格短編の第一人者だった。通俗がかった探偵小説の多かった時代に、これだけ本格物のテクニックを身につけた作家のいたことは、奇蹟という他はない。
|
「甦る幻の探偵作家たち −若い読者に−」
(国書刊行会「探偵くらぶ」内容見本 1992年5月)
|
|
法月綸太郎
|
戦前の日本にこんなセンスのいい本格があるとは、奇跡です。
|
「ミステリ研の新入生に読ませたい「国内本格ミステリ」Best10」
(「ブルータス」 1996年5月15日号(No364))
|
|
有栖川有栖
|
戦前の作家を紹介するアンソロジーを開くと、必ず大阪さんの作品が名を連ねています。それもほとんどが、今読んでもびっくりするようなトリックを使った傑作ぞろいです。
|
「有栖が語るミステリ100」
(『有栖の乱読』株式会社リクルート 1997年3月28日)
|
|
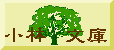
(C)小林文庫
|

E-mail
|
|